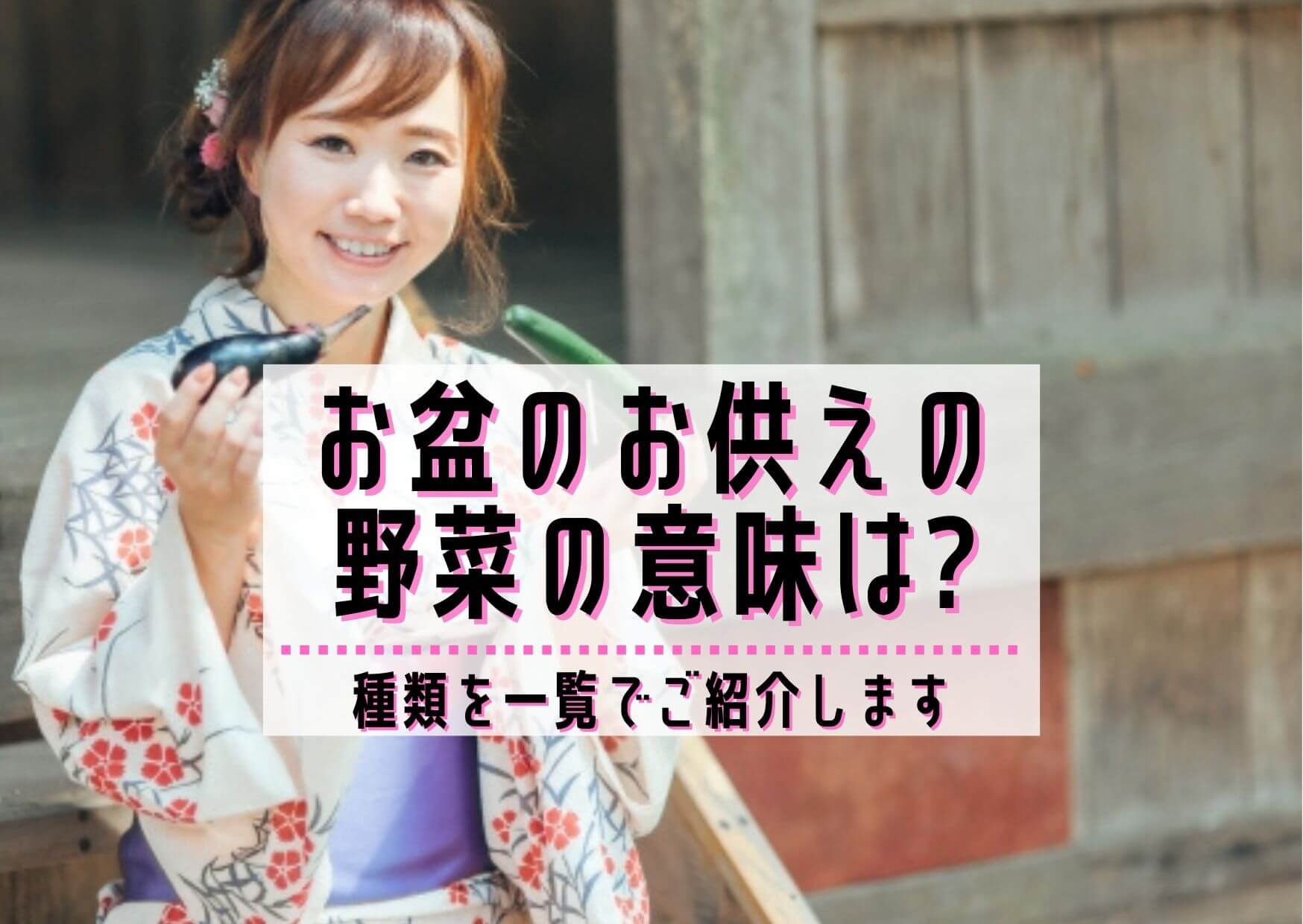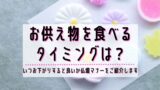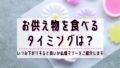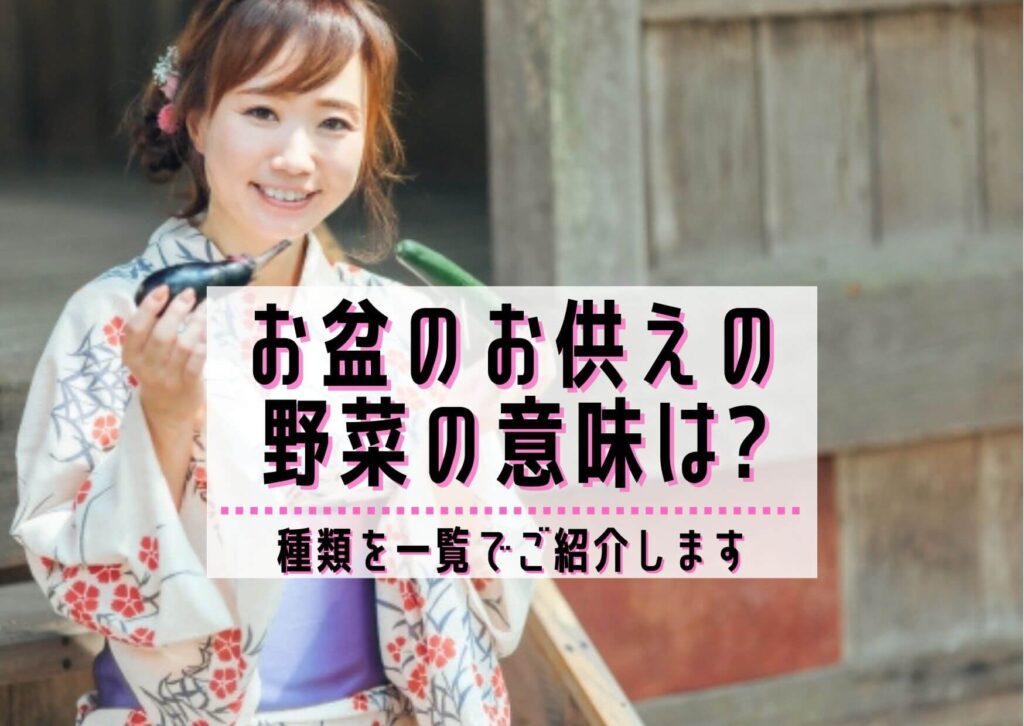
お盆にお供えする野菜や果物の意味は何なのでしょうか。お盆のお供え物の野菜と果物の種類を一覧でご紹介いたします。
お盆にお供えする野菜や果物と言いますと、きゅうりやなすを動物の形にした「精霊馬」をイメージされるかたが多いと思いますが、他にもいろいろな種類の野菜や果物があります。
また、お盆にお供えする野菜や果物には、ちゃんと意味もあるんです。
お盆のお供え物の野菜や果物の種類を一覧でご紹介しますので、ぜひ、精霊馬の他にお盆にお供えする野菜や果物の意味についてお知りになってください(*^^*)。
こちらの記事では、お盆にお供えする野菜や果物の意味が知りたい!と思われているかたの以下の疑問にお答えします☟。
どうぞ、お盆にお供えする野菜や果物の意味をお知りになる際のご参考になさってください(*^^*)。
お盆のお供え物の野菜や果物の種類と意味

お盆のお供え物の野菜や果物の種類と意味は次の通りです☟。
| 種類 | 意味 |
|---|---|
| ウリ科の野菜(キュウリ・カボチャ・ズッキーニなど) | ウリ科の野菜は種がたくさん入っていることから「生命力」や「子孫繫栄」を意味する |
| ナス | 「ナス=成す」を意味していて縁起が良い |
| マメ類(インゲン・ササゲ・サヤエンドウ・スナップエンドウなど) | 「まめに働く」で元気に健康でいられますように、また、たくさんの実を結ぶことができますようにという意味 |
| イモ類(ジャガイモ・サツマイモ・サトイモなど) | 土の中でたくましく成長する姿が「生命力」を、一つの親芋から次々と増えていく姿が「子孫繫栄」を意味している |
| 果物(スイカ・メロン・モモなど) | 丸い果物は「円=縁」を意味している |
お盆のお供え物にする野菜や果物を用意する際には、日持ちのするもの、においのきつくないものを選ぶと良いです。
精霊馬はなぜきゅうりやなすといった野菜を使うのか

お盆のお供え物の、きゅうりやなすといった野菜を動物の形にしたものを「精霊馬(しょうりょううま)」と言います。
精霊馬は、先祖の霊があの世とこの世を行き来する際の乗り物であると言われていて、きゅうりは動物の「馬」の形に、なすは動物の「牛」の形に見立てて作ります。
精霊馬には、こういった意味があります☟。
*精霊馬は、お盆のお供え物の一つですが、精霊馬を飾るのは東日本のみで、西日本では精霊馬ではなく、麦わらや木を使って「精霊船」を作るそうです。
精霊馬を作るのに、なぜきゅうりやなすを使うのか?ということについては、理由ははっきりとは分かっていないようです。
ただ、もともとお盆にお供えする野菜というのは、自宅で収穫できた野菜でしたので、お盆の時期にたくさん採れるきゅうりやなすが、精霊馬を作るのに使われたと考えられているようです。
また、きゅうりやなすは温度や湿度などの環境の変化に影響されにくい栽培しやすい野菜であるため、各地域で作られていたということも理由の一つのようです。
精霊馬の作り方

精霊馬の作り方と飾り方をご紹介します(*^^*)。
きゅうりやなすなどの野菜は、反りがあるものの方が動物らしく見えます。
きゅうりに使う割り箸は長めにすると馬らしく、なすに使う割り箸は短めにすると牛らしく見えます。
また、精霊馬は好みの形にアレンジしても問題ありません。動物でなくても大丈夫です(*^^*)。
「精霊馬 アレンジ」や「精霊馬 アート」でネット検索をすると、精霊馬の作品例がたくさん見つかりますので、先祖の霊に喜んでもらえそうな精霊馬を作るのも良いと思います。
お盆にお供えする野菜や果物を飾る期間

お盆にお供えする野菜や果物を飾る期間は、迎え火をする「盆入り」から、送り火をする「盆明け」までです。
お盆の期間は地域によって異なります☟。
【精霊馬の飾り方】
精霊馬の飾り方は、お盆の時期に用意する「精霊棚」に飾るのが一般的で、位置は精霊棚の両端や右側に段違いで、また、お供え物の一番奥に対で置くなど、地域によってさまざまです。
さらに、精霊馬を飾るときの向きには決まりがあります。
きゅうりで馬の形に作った精霊馬は先祖の霊をお迎えするものですので、頭が家の中を向くように、なすで牛の形に作った精霊牛は先祖の霊をお送りするものですので、頭が家の外を向くように飾ります。
また、盆入りにはどちらも頭が家の中を向くように飾り、盆明けにはどちらも頭が家の外を向くように途中で向きを変える飾り方もあります。
精霊馬の飾り付けは、お住まいの地域やその家庭のしきたりに合わせます。
お盆にお供えする野菜や果物の処分方法

お盆にお供えする野菜や果物の処分方法は次の通りです☟。
精霊馬以外の野菜や果物のお供え物は食べて良いですが、精霊馬は先祖の霊の“乗り物”として作ったものですし、お盆の時期に数日間飾って傷んでいたりもするでしょうから、食べるということはしません。
【精霊馬】
昔のように精霊馬を海や川に流す、燃やすといった処分方法は、今ではNGです。
精霊馬の処分方法としては、塩で清めてから家庭ごみとして捨てる、または、土に埋めるといった方法がやりやすいと思います。
精霊馬を塩で清めるときには、白い紙の上に置いた精霊馬の左側⇒右側⇒中央の順番に塩をかけて包みます。
また、お寺によっては精霊馬の「お焚き上げ」を行っているところもあるようですので、お焚き上げで精霊馬を処分したい場合にはお近くのお寺に問い合わせをしてみてください。
【精霊馬以外の野菜や果物のお供え物】
精霊馬以外の野菜や果物のお供え物は、家族でいただくか、親戚や友人と分け合うのが良いです。
仏壇にお供えした野菜や果物を「お下がり」をして食べることで、仏様やご先祖様と繋がることができると考えられています。
また、お供えした野菜や果物をいただくことは、亡くなったかたの冥福を祈る供養にもなります。
『お盆のお供えの野菜の意味は?種類を一覧でご紹介』まとめ
お盆のお供え物の野菜や果物の種類と意味を一覧でご紹介しました。
お盆にお供えする野菜や果物の意味をお知りになる際のご参考になりますと嬉しいです(*^^*)。
*
*
最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。