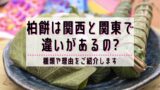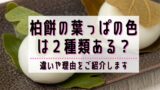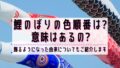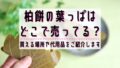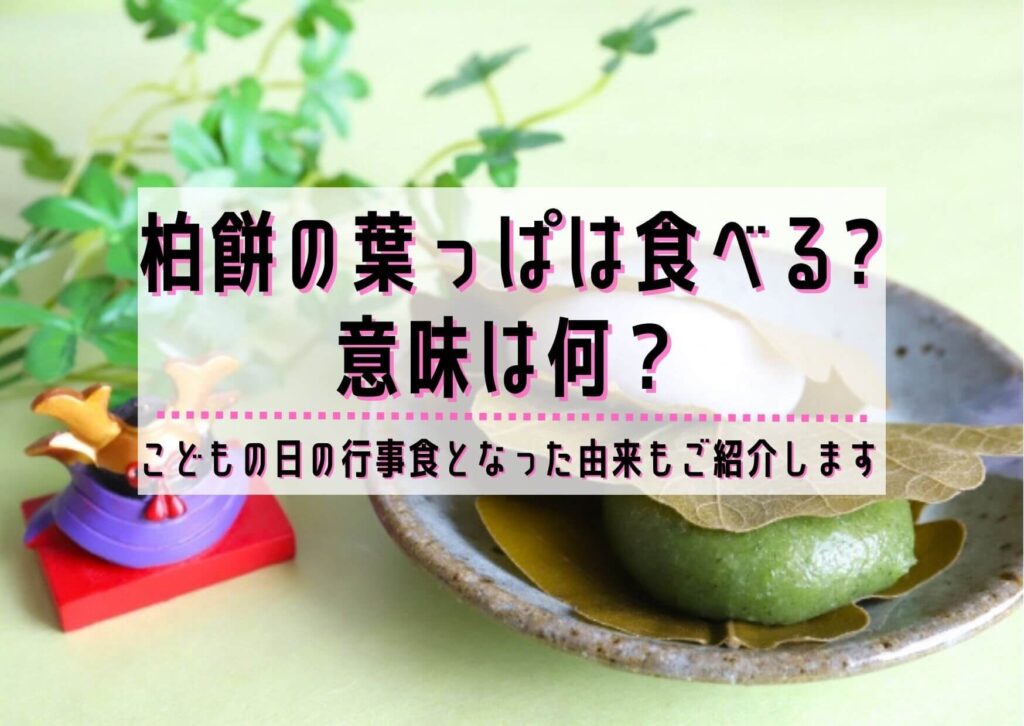
柏餅の葉っぱは食べるのでしょうか。また、柏餅の葉っぱには何の意味があるのでしょうか。こどもの日の行事食となった由来もご紹介いたします。
こどもの日の行事食、「柏餅」。
毎年、こどもの日が近づいてくると、お店などでは柏餅をよく見かけますし、ほとんどのかたが一度は柏餅を食べたことがあるのではないでしょうか。
ところで、この柏餅。葉っぱは食べるのか食べないのか、また、何の意味があって柏餅には葉っぱが巻かれているのか、よく分からなかったりしますよね(^^;。。
柏餅の食べ方や葉っぱの意味を知って、柏餅をおいしくいただきましょう(*^^*)。
こちらの記事では、柏餅の葉っぱは食べるのか、そして意味は何なのか知りたい!と思われているかたの以下の疑問にお答えします☟。
どうぞ、柏餅の葉っぱは食べるのかでお悩みの際のご参考になさってください(*^^*)。
柏餅の葉っぱは食べない

柏餅の葉っぱは食用目的では使われていませんので、食べることはしません。
柏餅の葉っぱは食べても害はないとされていますが、その独特の苦みや筋っぽい食感は、一緒に口にすると柏餅のおいしさを悪くしてしまいます(^^;
(ちなみに、「桜餅」の葉っぱは食べることができるので、桜餅の葉っぱを食べるか食べないかは好みで決めて良いです。)
また、柏餅の葉っぱには緑色と茶色の2種類がありますが、それは、加工方法や保存方法が違うためです。
いずれにしても、柏餅の葉っぱは食べるということはせず、葉っぱの中のお餅のみをおいしく召し上がってください(*^^*)。
柏餅の葉っぱの意味

柏餅の葉っぱにはこういった意味があります☟。
柏餅の葉っぱには、縁起の良い意味と、実用的な意味があるんですね(*^^*)。
・柏の葉っぱは「子孫繫栄」を意味する縁起物
柏餅に柏の葉っぱが巻かれている理由は、柏の葉が「子孫繫栄」を意味する縁起物だからです。
柏の葉っぱは秋には枯れますが、春に新しい芽が出るまで落ちません。
そのため、柏の葉っぱは、「親から子へと代が途切れない=子孫繫栄」を意味する縁起の良いものとされています。
古来より神聖な木とされてきた「柏」。
もともと神事には餅をお供えしていましたが、男の子の健やかな成長を願う日である「端午の節句」に食べる餅には、その意味にふさわしく柏の葉っぱが巻かれています。
*「端午の節句」は、1948年(昭和23年)に「こどもの日」として国民の祝日に制定されました。
・柏の葉っぱには「食べ物を乗せる器」の意味がある
子孫繫栄という意味の他にも、殺菌作用や保湿作用、香りづけ、食材同士のくっつき防止の目的で、柏餅には柏の葉っぱが巻かれています。
「柏」には“食べ物を料理するための道具” “食べ物を乗せる器”の意味があります。
柏の葉っぱは丈夫で、さらに、殺菌作用のある香り成分も含まれているために、昔は食器や保存の目的で使われていたそうです。
「かしわ」と読む樹木には、ヒノキ科の針葉樹である「柏」とブナ科で広葉樹の「槲」の二つがあり、柏餅に使われている葉っぱは「槲」の方ですが、現在では「柏」と「槲」は同じものを指すことが多いようです。
こどもの日に柏餅を食べるようになった由来

もともと宮中行事であった「端午の節句」は、「菖蒲」を用いて邪気祓いをするというものでした。
それが武士の時代になると、「菖蒲」と「尚武」の音が通じるということで武家が重んじる日へと変わり、男の子の成長を願う行事となりました。
柏餅が食べられるようになったのは、江戸幕府が5月5日の端午を重要な式日と定めた頃からだそうです。
幕府の首都であった江戸では、端午の節句に柏餅を食べるという風習が定着し、「参勤交代」によって各地に広まったようです。
『柏餅の葉っぱは食べる?意味は何?こどもの日の行事食となった由来』まとめ
柏餅の葉っぱは食べるのか、また、柏餅の葉っぱには何の意味があるのか、こどもの日の行事食となった由来もご紹介しました。
柏餅の葉っぱは食べるのかでお悩みの際のご参考になりますと嬉しいです(*^^*)。
*
*
最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。