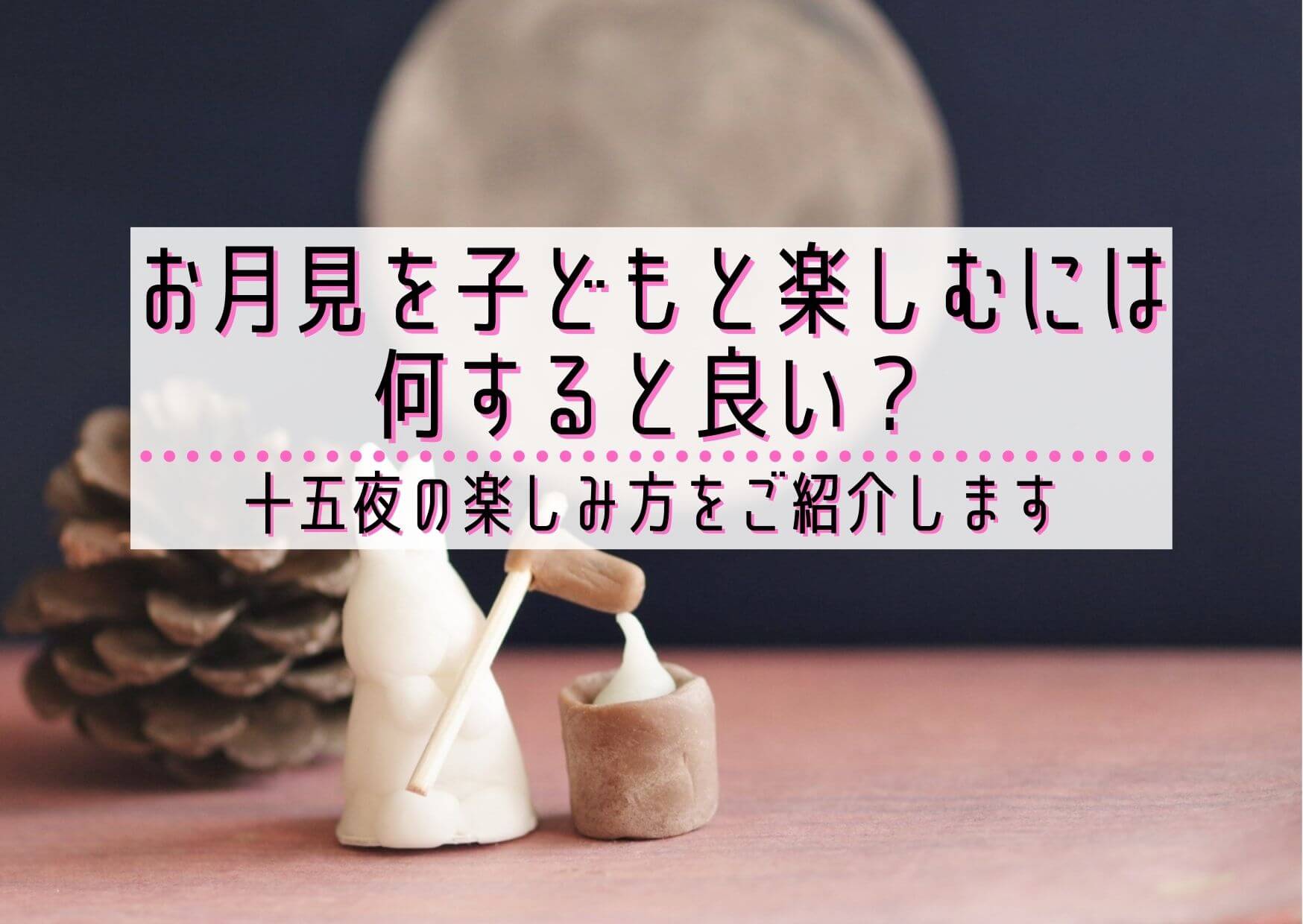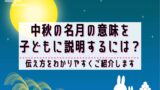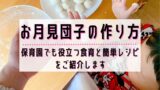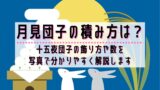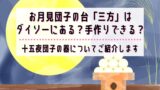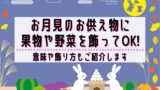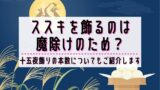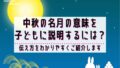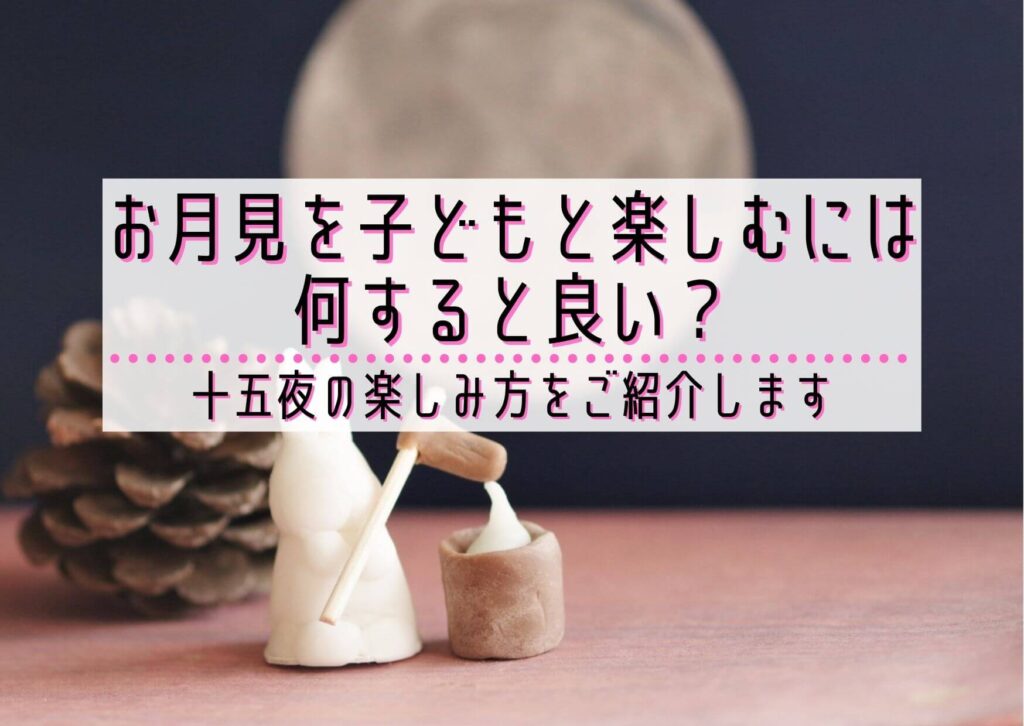
お月見を子どもと楽しむには何すると良いでしょうか。子どもとお月見を楽しむ方法をご紹介いたします。
小さな子どものいる家庭では、日本の行事を楽しむことが多いのではないでしょうか。
日本の行事には様々なものがありますが、「お月見」もその一つ。
でも、お月見を子どもと楽しむには具体的に何すると良いか、ちょっと分からなかったりしますよね(^^;
お月見を子どもと楽しむ方法は月を眺める以外にも色々ありますので、お月見の楽しみ方を知って、子どもと一緒にお月見の行事を楽しみましょう(*^^*)
こちらの記事では、お月見を子どもと楽しむには何すると良いか知りたい!と思われているかたの以下の疑問にお答えします☟
どうぞ、お月見を子どもと一緒に楽しむには何すると良いか、ご参考になさってください(*^^*)
お月見の意味は「収穫祭」

お月見は「中秋の名月」や「十五夜」とも呼ばれますが、どういった意味合いがあるのかご存知でしょうか。
お月見には「収穫祭」としての意味があります。
旧暦の8月15日に美しい月を鑑賞しながらお供え物をして、月の神様に豊作への祈りと感謝の気持ちを捧げます。
このお月見、もともとは中国から入ってきた風習であり、最初はただ美しい月を鑑賞するといった上流社会の間だけの風雅な催しだったそうです。それが後に庶民の間にも広がり、この時期に収穫できる食べ物に感謝する収穫祭と結び付いたのですね(*^^*)
ちなみに、旧暦では7・8・9月を秋としていたため、その真ん中の8月15日を「中秋(ちゅうしゅう)」と呼びます。また、「十五夜」は満ち欠けによる月の呼び名で、毎月15夜目の月のことを言いますが、通常は旧暦の8月15日の夜に見られる月(中秋の名月)を指します。
☟お月見の意味を子どもに分かりやすく説明する方法をご紹介しています(*^^*)
お月見を子どもと楽しむ方法

現代では、お供え物をして、きれいな月を眺めながら、食べ物への感謝と健康を願うのが「お月見」です。
お月見を子どもと楽しむには、具体的にはこういったことをすると良いですよ(*^^*)
・子どもと一緒にお月見団子を手作りする
お月見団子は作り方が簡単ですので、小さな子どもも一緒に作ることができます。
子どもと一緒にお月見団子を手作りすると、お月見を楽しむことができると思います(*^^*)
☟お豆腐を使ったおいしいお月見団子のレシピをご紹介しています。
・子どもと一緒にお月見団子を飾り付ける
子どもと一緒にお月見団子を手作りしたあとは、お月見団子をお月見の雰囲気たっぷりに飾り付けましょう(*^^*)
実は、お月見団子の積み方や数には決まりがあります。
お月見団子の積み方は難しくありませんので、ぜひ、子どもにお手伝いをしてもらいましょう。
☟こちらの記事で、お月見団子の飾り方を詳しくご紹介しています。
また、お月見団子を「三方」に乗せると、お月見の雰囲気をより楽しむことができると思います(*^^*)
☟こちらの記事で、お月見団子を乗せる台について詳しくご紹介しています。
お月見団子と一緒に、お月見の時期に旬の野菜や果物をお供えするのも良いです。
別名「芋名月」の十五夜には里芋を、別名「栗名月」「豆名月」の十三夜には栗や大豆をお供えします。
☟お月見に飾ると良い野菜や果物について詳しくご紹介しています。
・子どもと一緒にススキを飾る
お月見と言えば、お月見団子ともう一つ、ススキが欠かせません。
お月見団子とススキを一緒に飾るときには、月から見て左側にススキを、右側にお月見団子を飾ります。
また、ススキと一緒に、ススキ以外の「秋の七草」をお供えするのも良いです(*^^*)
☟ススキの飾り方やお月見のお供え物の配置について詳しくご紹介しています。
・子どもと一緒に月を眺める
やはり、お月見を楽しむには、子どもと一緒にきれいな月を眺めるのは欠かせません(*^^*)
この時期の月は、地表からの高さが大気に邪魔されない、かつ、見やすい位置にあることと、空気が乾燥しているために、一年で最もきれいに見えます。
【二夜の月、片見月】
お月見は、「十五夜」のあとに、「十三夜」にもするのをご存知でしょうか?
「十五夜」と「十三夜」に見られる二つの月を合わせて、「二夜の月(ふたよのつき)」と言います。
「十五夜」と対をなす「十三夜」、どちらか一方の月しか見ないことを「片見月」と言い、縁起が悪いとされているんです。
ぜひ、「十三夜」も「十五夜」と同様にお月見を楽しみましょう!
☟2026年の「十五夜」と「十三夜」の日程です。どうぞ、お子さまと一緒にお月見を楽しんでくださいね(*^^*)
お月見を子どもと楽しむアイディア
お月見を子どもと楽しむためのアイディアをご紹介します。
<お月見の歌>
お月見の歌にもいろいろありますが、「出た出た月が」はメロディーや歌詞が分かりやすいので、大人はもちろん、小さな子どもでも歌いやすいです(*^^*)
まずは、大人が子どもに歌ってあげてみてください。
<お月見の絵本>
お月見をテーマにした絵本を子どもに読み聞かせるのも良いです(*^^*)
絵本を読み聞かせることで、子どももお月見に興味を持つことができますし、大人も子どもも一緒に楽しむことができると思います。
「絵本ナビ」という絵本や児童書の情報を紹介しているサイトでは、試し読みをすることができるので、子どもの年齢や好みで絵本を選びやすいです。
お月見におすすめの絵本も多数紹介されていますので、ぜひ、見てみてください(*^^*)
<お月見ウサギの折り紙>
子どもと一緒に、お月見ウサギの折り紙をして遊ぶのも楽しいと思います。
こちらのかわいいウサギの折り方は、「ばぁばさん」というかたが優しく丁寧に説明してくださっています。
折り紙2枚を使いますが、1枚で顔だけ折っても楽しめますよ(*^^*)
完成したウサギの折り紙は、子どもと一緒にお部屋に飾り付けをすると、よりお月見を楽しむことができますね。
お月見のお供え物と意味
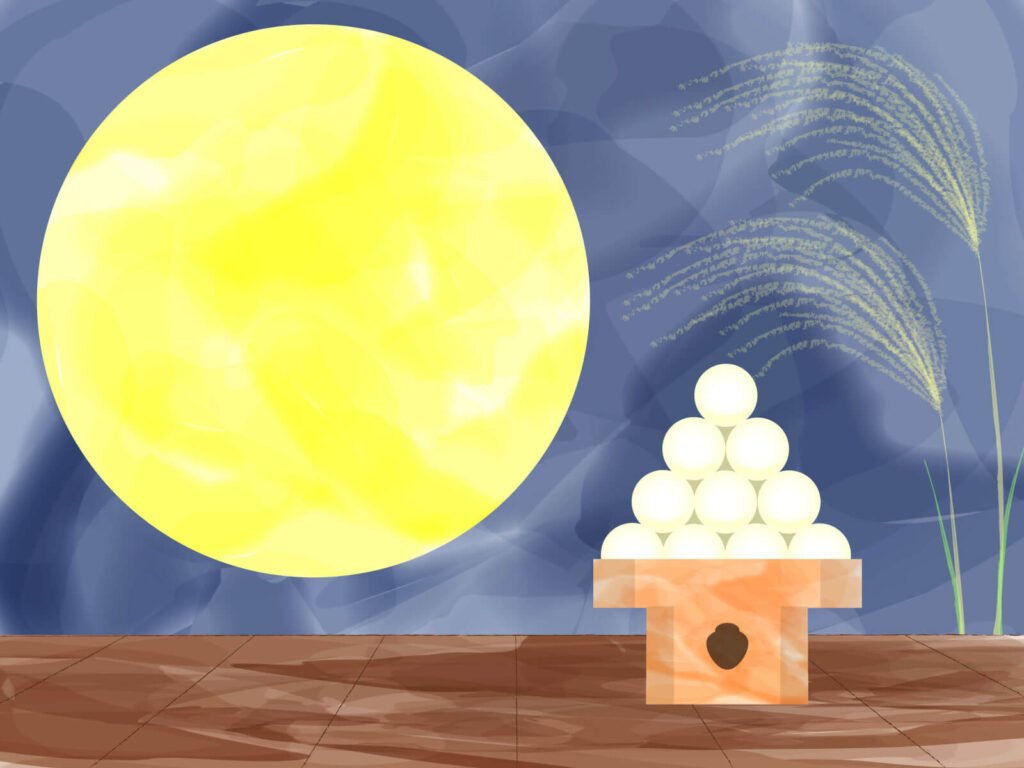
お月見のお供え物にはこういったものがあります☟
それぞれのお月見のお供え物の意味についても見てみましょう☟
ぜひ、お子さまにもお月見のお供え物の意味について説明してあげてください(*^^*)
・お月見団子
お月見団子は月の神様へのお供え物です。
もともとはその時期に収穫した野菜や果物をお供えしていたそうですが、江戸時代からは、お米の粉で月に見立てた丸いお団子を作るのが習慣になったそうです。
お月見団子をピラミッド型に高く積むのには、豊作への祈りと感謝の気持ちを月まで届かせたいという思いが込められています。
農作業は月齢を基準とした太陰暦をもとに行なわれていたため、月の神様には五穀豊穣のご利益があるとされていました。
・ススキ
ススキには月の神様を呼ぶ「依り代」としての意味があります。(依り代は神霊のよりつくもののこと)
本来は稲穂をお供えするところ、時期的に稲穂がなかったために、形の似ているススキを飾るようになったということです。
また、ススキの切り口は鋭く「魔除け」になると考えられてきました。ススキをお供えするのには無病息災の願いも込められているのですね。
・野菜や果物
野菜や果物をお供えするのには、お月見団子と同じく、豊作への祈りと感謝の意味があります。
里芋や栗、大豆の他にも、お月見団子やススキと一緒に、お月見の時期に旬の野菜や果物をお供えするのも良いです。
『お月見を子どもと楽しむには何すると良い?楽しみ方』まとめ
お月見を子どもと楽しむには何すると良いのか、子どもとお月見を楽しむ方法をご紹介しました。
お月見には「収穫祭」としての意味があり、現代では、お供え物をして、きれいな月を眺めながら食べ物への感謝と健康を願う、といったことをする。
お月見を子どもと一緒に楽しむには何すると良いか、ご参考になりますと嬉しいです(*^^*)。
*
*
最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。