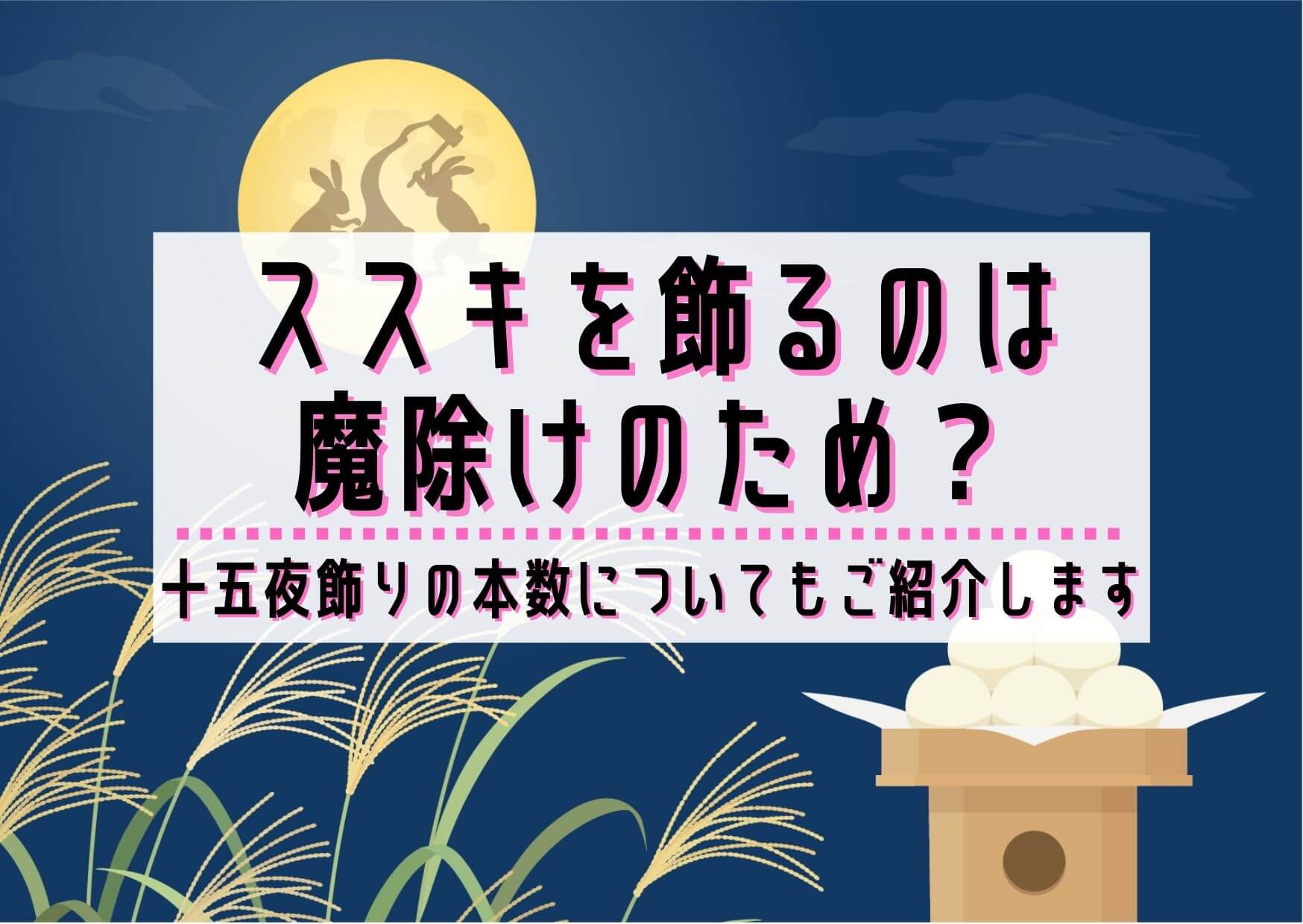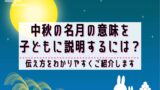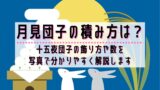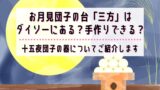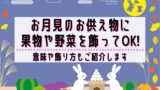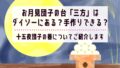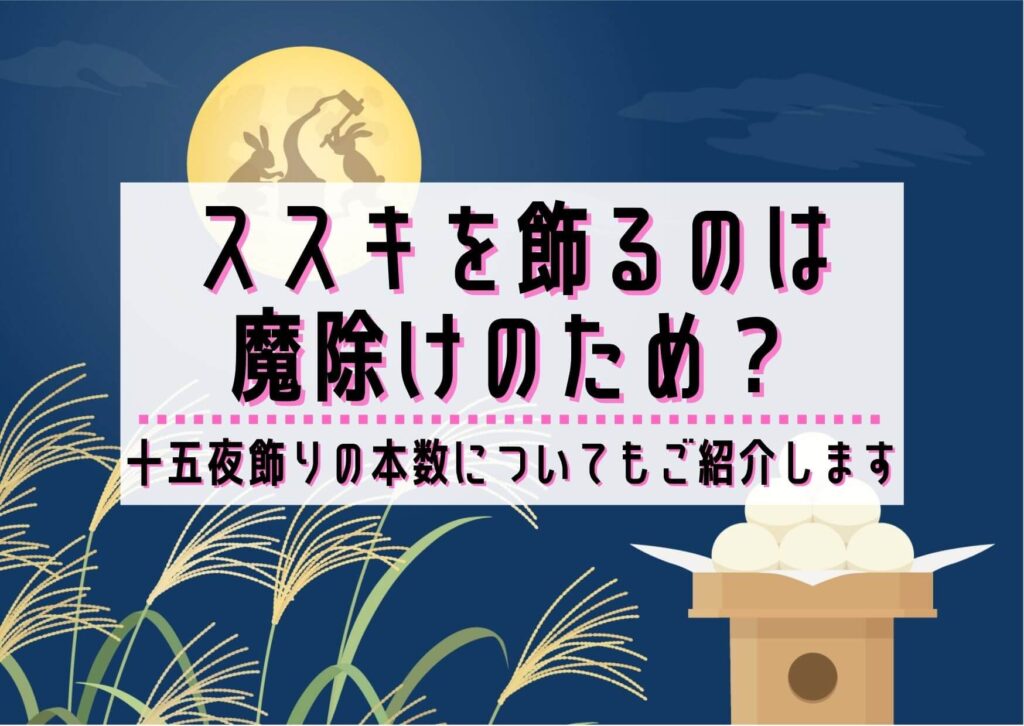
ススキを十五夜のお月見に飾る意味は何なのでしょうか。また、本数や配置には決まりがあるのでしょうか。十五夜のお月見飾りの意味や飾り方についてご紹介いたします。
秋の七草の一つ「ススキ」。
十五夜にお月見をするときには、お月見団子と一緒にススキを飾るかたは多いのではないでしょうか。
ですが、十五夜のお月見飾りと聞いてなんとなくススキをイメージできても、どうして十五夜にススキを飾るのか、ちゃんと分からなかったりしますよね。。
また、十五夜のお月見でススキを飾るときに、ススキの本数や他のお供え物との配置はどのようにしたら良いのか、迷ってしまいそうです。
こちらの記事では、十五夜のお月見にススキを飾る意味やススキの飾り方を知りたい!と思われているかたの以下の疑問にお答えします☟。
どうぞ、十五夜のお月見にススキを飾る際のご参考になさってください(*^^*)。
ススキを飾る意味は「依り代」と「魔除け」

十五夜にススキを飾るのにはこういった意味があります☟。
まず、お月見には「収穫祭」としての意味があります。
中国から渡ってきたこの風習は、最初はただ美しい月を鑑賞するといった上流社会の間だけの催しでしたが、江戸時代には庶民の間にも広がり、この時期に収穫できる食べ物に感謝する収穫祭と結びつきました。
そして、十五夜にススキを飾るのには「依り代」と「魔除け」の二つの意味があります。
農作業は月の満ち欠けに合わせて行われていたために、月には五穀豊穣のご利益がある神様がいるとされていました。
この、神様を呼ぶ「依り代」がススキです。*依り代とは神霊のよりつくもののこと
本来は稲穂をお供えするところ、稲刈り前で稲穂がなかったために、代わりに形の似ているススキを稲穂に見立ててお供えするようになったということです。
また、ススキをお供えするのには「魔除け」になると考えられていたからでもあります。
ススキの切り口が鋭い、というのがその理由。ススキを飾るのには、豊作祈願と合わせて無病息災の願いも込められていたのですね(*^^*)。
十五夜のススキの飾り方

十五夜のススキの飾り方には決まりはあるのでしょうか。
瓶子とは神様にお酒をお供えするための器で、口がすぼまった壺のような形をしています。
とは言いましたが、十五夜のススキの飾り方は自由で大丈夫ですよ(*^^*)。
ただ、ススキを素敵に飾るにはちょっとしたコツがありますのでご紹介します。
十五夜に飾るススキの本数は奇数
十五夜に飾るススキの本数に決まりはありませんが、通常、生け花は3本、5本といった奇数で扱います。
それは、左右非対称の方が動きが出て良いとされているからです。
また、割り切ることのできる偶数は別れを連想させるため、縁起の悪い数字とされ、香典や結婚式などのご祝儀でも避けられます。(8は例外です)
というわけで、十五夜に飾るススキは奇数本を用意しましょう(*^^*)。
ススキはお月見シーズンになればお花屋さんで手に入れることができます。
ススキは日持ちが悪く、もって3日ほどですので、お月見をする直前に用意されると良いです。
秋の七草を組み合わせる
ススキは尾花(おばな)とも言い、秋の七草の一つですが、十五夜にはススキと一緒に他の秋の七草を飾るのも良いですよ(*^^*)。
ススキを他の秋の七草などと一緒に飾る場合は、まず、かさのある花を、その後にススキを生けます。
そうすることで、かさのある花がススキの長い茎を支えてくれるので安定します。
同じ種類の花は長さを数センチずつ変えて段差を付け、ススキは他の花よりも高くして目立たせると良いです。
ススキ以外のお供え物と一緒に飾る
十五夜のお供え物はススキ以外にもあります☟。
こういったものをススキと一緒に飾るのも良いですよ(*^^*)。
【お月見団子】
お月見団子を飾るのが習慣になったのは江戸時代からだそうです。
お月見団子はピラミッド型に高く積まれていますが、これは、感謝の気持ちと豊作の祈りを月の神様まで届かせたいという思いの表れです。
☟お月見団子の飾り方について詳しくご紹介しています。
【里芋、この時期に旬の野菜や果物】
十五夜の別名は「芋名月」と言われていて、お月見の時期に収穫期を迎える里芋も飾ります。
里芋の他に、この時期に旬の野菜や果物も一緒に飾るのも良いです(*^^*)。
☟十五夜に飾ると良い野菜や果物について詳しくご紹介しています。
ススキは月から見て左側に配置する

お月見のお供え物の配置には決まりがあります。
ススキとお月見団子と野菜を一緒に飾る場合は、月から見て左側にススキや野菜を、右側にお月見団子を配置します。
これは、中国から入ってきた「左上右下」の考え方で、左を上位、右を下位とするものです。
月から見て上座となる左側にススキや野菜などの自然界のものを、右側にお月見団子などの人工的なものを飾ります。
「左上位」のしきたりは私たちの日常生活にも根付いていて、例えば、着物の襟合わせも自分から見て左襟が右襟よりも上になるように着付けますし、障子やふすまのはめ方も左側が上になります。
『ススキを飾るのは魔除けのため?十五夜飾りの本数について』まとめ
十五夜のお月見にススキを飾る意味、ススキの本数や配置など、十五夜のお月見飾りについてご紹介しました。
十五夜のお月見にススキを飾る際のご参考になりますと嬉しいです。
*
*
最後まで読んでくださいまして、ありがとうございました。